アパート投資の初期費用額の目安と内訳を解説!100万円で始められる?
アパート投資を始めるにあたって必要になるのが「初期費用」です。
初期費用は、物件購入時の頭金や事務手数料・税金などの諸費用が含まれますが、基本的に自己資金で支払うため、どの程度の金額になるのか把握しておく必要があります。
そこで今回はアパート投資の初期費用について、おおよその初期費用の目安と内訳、初期費用に関する注意点について解説します。
これからアパート投資を始める方は、ぜひ参考にしてください。


アパート投資で必要な初期費用額に目安

アパート投資を始める場合、物件の取得費用の一部を「初期費用」を自己資金でまかない、残りの大部分の額は金融機関から融資(アパートローン)を受けるのが一般的です。
ここではアパート経営で必要な初期費用額について、以下のパターンごとの目安額を紹介します。
◦アパート投資で必要な初期費用額の目安
◦アパート投資でフルローンを利用する際の初期費用額
◦アパート投資は初期費用100万円でも始められる?
アパート投資で必要な初期費用額の目安
アパート投資の初期費用とは、物件購入代金以外にかかる「諸費用」や「頭金」のことを指し、どちらも自己資金から支払うのが一般的です。
諸費用は主に、物件購入(建築)の手続きに関係する手数料・各種税金・保険料などが該当します。
諸費用の目安は物件価格の5%~10%程度ですが、新築か中古か、建売か建築するかなどによって多少増減します。
一方で頭金は、物件の購入(建築)費用の一部を自己資金で支払う先払い金のことで、物件価格の1割~3割程度が目安となります。
頭金の額に決まりはありませんが、頭金を多く入れることで金融機関からの借入額を減少できるため、ローン返済時の利息や返済額の負担を軽減することが可能です。
また、融資審査に有利になったり、金融機関によっては低金利などの優遇を受けられたりする可能性が高まります。
アパート投資に必要な初期費用額はいくら?
前述したように、アパート投資に必要な初期費用は、頭金と諸費用の額によって決まります。
たとえば、3,000万円の中古一棟アパートを購入するケースを考えてみましょう。
【3,000万円の一棟アパート購入時に必要な初期費用額】
◦頭金:300万円~900万円(物件価格の1割~3割)
◦諸費用:150万円~300万円(物件価格の5%~10%)
3,000万円の一棟アパート購入時に必要な初期費用額は、450万円~1,200万円となります。
必要な初期費用額は、頭金をどのくらい入れるか、仲介手数料の有無などによって変わるため、初期費用を抑えたい場合は、仲介手数料が発生しない「売主物件」を選ぶなどするとよいでしょう。
なお、頭金は多ければ多いほど融資審査で有利となり、月々のローン返済にも余裕が生まれます。
どの程度の頭金を入れるかによって必要な自己資金額も変わってくるため、まずは資金面のシミュレーションをおこない、十分な収入が見込めるか、無理なくローン返済ができるかなどをしっかり確認しましょう。
アパート投資でフルローンを利用する際の初期費用
前述したようにアパート投資を始める際は、物件価格の1割~3割程度を「頭金」として支払い、残りの額についてローンを組むのが一般的です。
ただし、頭金なしで金融機関から融資を受ける方法もあります。それを「フルローン」と言います。
フルローンは頭金なしで融資を受けることができるため、アパート投資を始める際の初期費用を大幅に抑えることが可能です。
たとえば、前述した3,000万円の一棟アパートをフルローンで購入した場合、必要となるのは諸費用150万円~300万円(物件価格の5%~10%)となります。
また手元に自己資金を残しておくことができるため、万が一に備えられるなどのメリットもあります。
ただしフルローンを利用した場合、頭金を入れない分、金融機関からの借入額は大きくなります。
そのため、空室が増えて家賃収入が減少したり、突発的な支出があったりした場合、月々のキャッシュフローが悪化しやすくなるため注意が必要です。
アパート投資の返済原資は家賃収入であるため、家賃収入が減りローン返済などができなくなると、給与や貯蓄などから手出しが必要になるリスクが高くなります。
またフルローンは融資額が大きくなるため、頭金を入れる場合よりも金融機関の融資審査は厳しいのが一般的です。
融資審査に通過しなければフルローンで融資を受けることはできません。
なお、フルローンであっても諸費用は自己資金から支払う必要があります。
頭金が不要で諸費用も含めて借入できる「オーバーローン」という選択肢もありますが、フルローンよりもさらに借入額が大きくなるため、返済リスクが高くなることが懸念されます。
フルローンやオーバーローンを検討する際は、しっかりとキャッシュフローが確保できるか、資金に余裕があるかなどを確認したうえで利用することをおすすめします。
関連記事:アパート投資のフルローンはハイリスク?メリットとデメリットを解説
関連記事:アパート投資で手出し(赤字)になりやすい物件の特徴を解説!
アパート投資は初期費用100万円でも始められる?
アパート投資などの不動産投資は、物件購入費用の大部分を金融機関から融資を受けることができるため、少ない自己資金でも始めやすい投資方法です。
しかし、価格が高い一棟アパートを初期費用100万円で購入するのは、正直むずかしいです。
ただ選択する物件によっては初期費用(自己資金)100万円でも不動産投資を始めることは可能です。
初期費用(自己資金)100万円で始められる不動産投資には、以下のような種類が考えられます。
◦区分マンション投資
◦J-REITや不動産クラウドファンディングなど
区分マンション投資とは、マンションの1部屋だけを購入し、賃貸して家賃収入を得る不動産投資手法です。
特に地方や築年数の古い物件であれば、数百万円台の区分物件も多数あります。
ただし、築年数の古い物件は購入してから修繕費が嵩むケースが高いため注意が必要です。
購入してから「失敗した」と後悔しないためにも、水回り設備やエアコン、給湯器などがいつ導入されたか、マンションの建物の大規模修繕工事がいつおこなわれたかなどをしっかり確認しましょう。
また現物不動産投資ではありませんが、J-REIT(ジェイリート)や不動産クラウドファンディングのように複数の投資家から資金を集めて不動産に投資し、配当金や分配金を受け取る方法もあります。
現物不動産投資とは異なり、物件の選定・運用・管理はすべて専門家がおこなうため、投資家自身の負担が少ないのも魅力です。
関連記事:100万円でできる不動産投資!少ない自己資金で大家になる3つの方法
関連記事:不動産投資とリート(J-REIT)を比較!それぞれに向いてるのはどんな人?
アパート投資の初期費用(諸費用)の内訳

ここでは、アパート投資を始める際の初期費用のうち、諸費用の内訳について解説します。
仲介手数料
「仲介手数料」は、不動産会社を介して不動産売買が成約した際、仲介した不動産会社に支払われる成功報酬です。
仲介手数料は「宅地建物取引業法第46条」にて、上限額が決められています。したがって不動産会社は、その上限額を超える額の仲介手数料を受け取ることはできません。
仲介手数料の上限額は不動産の売買額によって変動し、以下の方法で計算します。
【仲介手数料の上限額】
◦200万以下の部分:取引額の5%以内+消費税
◦200万円を超えて400万円以下の部分:取引額の4%以内+消費税
◦400万円超の部分:取引額の3%以内+消費税
取引額が400万円を超える場合は、下記の計算式で仲介手数料の上限額を算出することができます。
【400万円を超える物件についての仲介手数料額】
◦仲介手数料 = 売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税
たとえば、2,000万円の不動産を購入した場合、上記の計算式で仲介手数料上限額を計算してみましょう。
(2,000万円 ✕ 3% + 6万円) ✕ 1.1 = 72万6千円
なお、仲介手数料には下限額は決められていません。
仲介手数料は決して小さな金額ではないため、初期費用を抑えたい場合はできるだけ仲介手数料を低く設定している不動産会社を選ぶとよいでしょう。
また個人の売主との直接取引や不動産会社が直接所有・販売する「売主物件」の場合、仲介手数料は発生しません。
ただし、個人間で直接取引をおこなう場合、売主・買主ともに不動産取引に関する知識が不十分であることも多く、売買契約がスムーズにすすまなかったり、トラブルに発展したりするケースもあるため注意が必要です。
関連記事:不動産投資の仲介手数料には上限額がある!仕組みや計算方法を解説
不動産取得税
「不動産取得税」は、不動産を取得した場合に課せられる税金です。
固定資産税とは異なり、不動産を取得したときのみに課せられます。
不動産取得税は以下の計算式で求めます。
【不動産取得税の計算式】
不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 税率4%(標準税率)
なお、特例により令和9(2027)年3月31日までは、土地および住宅の場合は標準税率が3%に軽減されます。
また不動産所得税の税率は各自治体によって異なる部分があるため、詳しくは各自治体で確認しましょう。
印紙税
10万円以上の「不動産売買契約書」や「金銭消費貸借契約書」などの書類には、契約金額に応じて「印紙税」を納める必要があります。
印紙税は売買契約の金額により、以下のように定められています。
【印紙税額】

引用:国税庁『印紙税の軽減措置の延長について』
なお、平成26年4月1日から令和9年3月31日までのあいだに作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるものについては、印紙税の軽減措置の対象となります。
登録免許税
不動産を購入した際は所有権や抵当権などの登記が必要となり、「登録免許税」が課せられます。
登録免許税は、以下の計算式で求めます。
登録免許税額 = 課税標準 × 税率
【登録免許税の税率】
◦土地の売買による所有権移転登記 : 2%(令和8年3月31日まで1.5%)
◦建物の売買による所有権移転登記 : 2%
◦所有権の保存登記 : 0.40%
◦抵当権設定登記 : 0.40%
司法書士への報酬
購入した不動産の登記手続きを司法書士に依頼する場合は報酬を支払います。
報酬額は、依頼する司法書士によって異なりますが相場は10万~15万円程度です。
なお、登記申請は個人でもおこなうことができます、必要な書類が多く、また手続きも慣れていない方には複雑なため司法書士に依頼するのがおすすめです。
固定資産税などの清算金
年の途中で不動産の売買がおこなわれた場合、その年の固定資産税について購入後の所有日数分だけ買主が負担するのが一般的です。
固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産所有者に課せられる税金です。
買主が固定資産税の精算金を支払うことで、売主は1月1日から不動産を買主に引き渡す前日まで、買主は不動産を引き渡された日から12月31日までの固定資産税を負担することになります。
そのため、不動産物件の引き渡し日によって清算金の額は変わってきます。
ローン(融資)事務手数料
不動産の購入資金を金融機関から借入れた場合、ローン手続きのための「ローン(融資)事務手数料」が発生します。
融資事務手数料は、以下の2種類があります。
◦定額型:借入金額に関わらず一定の金額を支払う。目安は3万円~10万円程度
◦定率型: 借入金額に対して設定された割合の額を支払う。目安は借入額の1%~3%程度
いずれも金融機関によって金額や割合が異なるため、詳細は融資を受ける金融機関に確認しましょう。
ローン保証料
不動産の購入資金を金融機関から借入れた場合、貸し倒れを防ぐためにローンの保証会社と契約することが一般的です。その場合に必要になるのが「ローン保証料」です。
ローン保証料の支払い方法は、借入時に一括で支払うか、または毎月の返済額に上乗せして支払うかのどちらかです。
借入時に一括で支払う場合は借入金額の2%程度を売買契約締結時に支払います。
返済額に上乗せする場合は、月々0.2%~0.3%程度を上乗せした利息を支払います。
ローン保証料は一括で支払う方が、支払い総額は安いですが、まとまった金額が必要です。
金利を上乗せする場合、毎月のローン返済額は増えますが、初期費用は抑えられます。
損害保険料
金融機関から融資を受ける際、ほとんどの場合で火災保険への加入が融資条件となります。
一棟アパートの損害保険額は、建物の構造・築年数・規模・立地・家賃収入などの物件の状態のほか、保険の契約期間や付加する特約などによっても違います。
そのため、平均や一般的な金額といった相場を提示することはむずかしいです。
まずは、物件の立地などから想定できる災害リスクに対する補償を考慮し、必要な特約だけを付けることで保険料を抑えられます。
アパート投資で初期費用に関する注意点
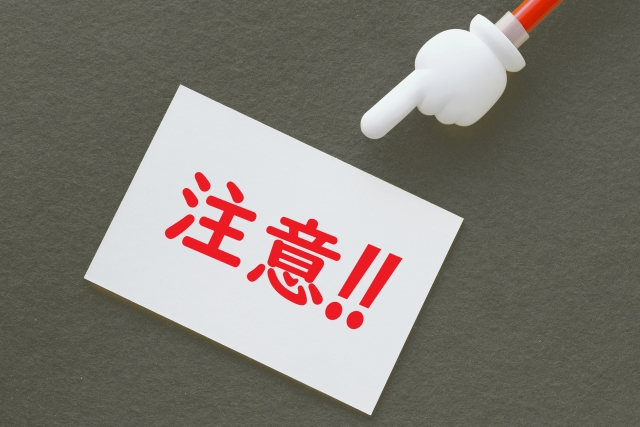
ここではアパート投資を始める際に準備する初期費用について、注意点を解説します。
初期費用とは別に自己資金を残しておく
アパート投資を始める際は初期費用とは別に、ある程度の資金を手元に残しておくことをおすすめします。
前述したように、初期費用のうち頭金を多く入れることで、有利な条件で融資を受けられたり、月々のローン返済の負担が軽減したりといったメリットがあります。
しかし、自己資金の大部分を初期費用に充ててしまい、手元の資金がほとんどないといった状態は、今後のアパート経営にとって非常に危険です。
アパート経営では、突発的な設備の故障など予期せぬ出費が発生する場合も少なくありません。
その際、自己資金が少ないと修繕や設備交換などへの対応が困難になる可能性があるため注意が必要です。
円滑なアパート投資をおこなううえで、万が一に備えてある程度の資金を手元に確保しておくことが重要なのです。
過度なコストカットは避ける
初期費用をできるだけ抑えたいと考える方は多いでしょう。
特に初期費用のなかで大きな割合を占める頭金は、物件価格の1割~3割程度入れるのが一般的ですが、もっと少ない頭金でも融資を受けることは可能です。
しかし、頭金を減らし過ぎると月々のローンの返済負担が重くなったり、融資審査にとおりづらくなったりする場合もあるため注意が必要です。
頭金を減らす場合は、あらかじめ収支シミュレーションをおこない、無理なくローン返済ができる物件を選ぶことが重要なポイントになります。
初期費用を抑えたい場合は、頭金を過度に減らすのではなく、仲介手数料が不要な「売主物件」を選んだり、損害保険のかけ過ぎに注意したり、報酬が安い司法書士を選んだりするとよいでしょう。
まとめ
アパート投資に必要な初期費用の目安は、頭金が物件価格の1割~3割程度、諸費用が物件価格の5%~10%程度となります。
ただし初期費用額は、物件の種類や築年数、借入額などによって変動します。
初期費用を抑えることも可能ですが、頭金を過度に減らしてしまうとローン返済の負担が重くなる場合もあるため注意が必要です。
逆に自己資金の大部分を初期費用にしてしまうと、突発的な出費の際に資金不足に陥ってしまうおそれがあります。
アパート投資を始める際は、初期費用と手元資金のバランスを考えて、どの程度の自己資金を用意すればよいのか、しっかり検討することをおすすめします。




