不動産投資におけるトラブルとその対策 〜リスクを理解し、堅実な投資を〜
夢の不動産投資、その裏に潜む「現実」

「家賃収入で安定した副収入を得たい」「将来の資産形成として不動産を持ちたい」 このような理由から、不動産投資を始める方は増加傾向にあります。しかし、表面上の収益性だけに目を向けてしまうと、思わぬトラブルに見舞われることも少なくありません。
不動産投資には、株式や投資信託と異なり「実物資産」を扱う特性があります。そのため、物件自体に関する問題はもちろん、入居者や管理会社など“人”との関係に起因するトラブルも発生しやすいのです。
本記事では、不動産投資を始めるにあたって知っておきたい主なトラブルの実例と、その予防策・対応策について解説します。あらかじめリスクを知っておくことで、堅実な投資判断につながるでしょう。
不動産投資に潜む主なトラブルと対策
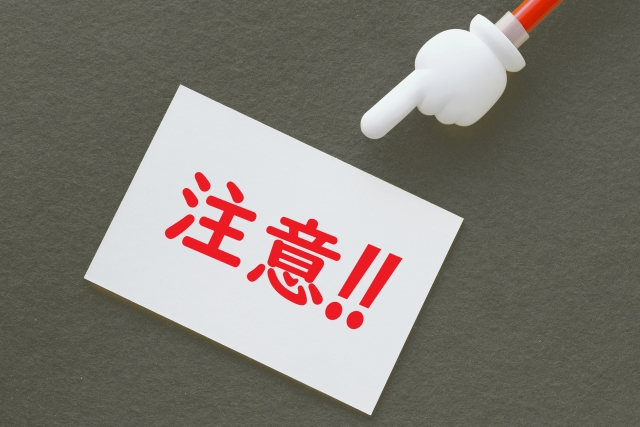
不動産投資における主なトラブルとは?
まずは、どのようなトラブルが発生しやすいのかを確認しましょう。以下のグラフは、実際に不動産投資を行うオーナーが直面した主なトラブルとその割合を示したものです。
1. 家賃滞納トラブル

事例: 契約当初は支払いも順調だった入居者が、半年後から家賃の支払いを遅らせるようになり、最終的には数ヶ月分の滞納が発生。連絡も取れなくなり、法的手続きに進むことになった。
原因: ・入居者の収入状況の変化 ・審査基準の甘さ ・連帯保証人が機能していないケース
対策: ・家賃保証会社の利用(保証制度を導入することで、滞納リスクを軽減) ・入居審査の厳格化(職業・収入・過去の履歴など) ・定期的な督促と記録の保存(法的対応時に備える)
専門的視点: 家賃保証会社との契約は、信用補完機能を果たす金融商品ともいえます。収益不動産のキャッシュフロー安定性を高めるうえで、今や必須といえる存在です。また、保証内容や免責事項をしっかり確認し、トラブル発生時の対応フローを事前に把握しておくことが重要です。
2. 空室リスク

事例: 駅から遠く築年数の経った物件を購入後、長期間空室が続き、想定していた利回りが大幅に下がってしまった。
原因: ・立地や周辺環境の競争力低下 ・物件の魅力不足(古さ・間取り) ・募集条件が市場ニーズに合っていない
対策: ・エリア選定時の需要調査(人口動向、周辺の賃貸状況) ・リノベーション・設備強化による差別化 ・賃料設定の見直し(市場平均との乖離チェック)
専門的視点: 空室リスクの管理は、"賃貸需要の定量評価"が鍵となります。たとえば、駅距離、築年数、間取り、設備の充実度、家賃帯などの各ファクターにスコアリングを行い、周辺物件との相対評価を可視化すると、リスク判断の精度が上がります。また、エリアによっては短期賃貸や法人契約の需要を見込めるケースもあり、多様な出口戦略を持つことが重要です。
3. 設備故障による対応

事例: 入居者から「エアコンが動かない」との連絡があり、修理業者の手配に時間がかかったため、入居者との関係が悪化。最終的に退去されてしまった。
原因: 設備の老朽化 、修繕対応の遅れ 、管理会社との連携不足
対策: 定期的な点検・更新 、緊急対応を含む管理体制の整備 、修繕費を見込んだ資金計画
専門的視点: 収益物件では、年間収支計画(プロフォーマ)のなかに「資本的支出(CapEx)」と「修繕維持費(OpEx)」を明確に区分して組み込む必要があります。これにより突発的な出費にも備えられ、長期的なIRR(内部収益率)の維持が可能となります。減価償却資産の耐用年数や法定点検サイクルも意識しながら、管理計画を構築することが大切です。
4. 近隣住民とのトラブル

事例: 入居者の生活音に対し、近隣住民から苦情が多数発生。トラブルが長期化し、地域での評判が悪化。
原因: ・入居者のモラル ・入居前の説明不足 ・管理体制の不備
対策: ・契約時の説明強化(騒音・ゴミ出しなど) ・苦情対応のマニュアル化 ・管理会社と連携し迅速に対処
専門的視点: このようなトラブルは「リスク顕在化後の対応スピード」が命です。コンプライアンスに関わる問題としても捉え、入居者管理と近隣配慮の観点から、事前に対応マニュアルを管理会社と共有しておくと有効です。また、民法改正による賃貸借契約の扱い変更(例:2020年4月施行)にも留意し、トラブル解決の根拠法令を明示できる体制が求められます。
5. 管理会社とのトラブル

事例: 管理会社が物件の点検や入居者対応を適切に行っていなかった。トラブルが放置された結果、空室が増加。
原因: ・委託内容の不明瞭さ ・報告義務の曖昧さ ・オーナーとの連絡不足
対策: ・管理契約書の内容を明確に ・定期的な報告・面談の実施 ・必要であれば管理会社の変更も検討
専門的視点: 不動産管理のアウトソーシングには、管理会社のKPI(Key Performance Indicator)設定が効果的です。具体的には「入居率」「原状回復期間」「クレーム対応スピード」などを数値化し、定期的に進捗レポートを共有させると良いでしょう。また、サブリース契約を含む一括借り上げ方式の場合、契約条件や解除条項の精査も不可欠です。
トラブルの理解が、堅実な不動産投資の第一歩

不動産投資には確かに収益の魅力がありますが、その裏にはさまざまなリスクが存在します。とくにトラブルは、想定していないタイミングで発生し、収益性に大きな影響を与えることがあります。
しかし、こうしたリスクは事前の知識と対策によって、ある程度予防・軽減することが可能です。
安定した不動産投資を実現するためのポイント
- トラブルの種類を把握しておく
- 良好な管理体制を構築する
- 情報収集と定期的な見直しを怠らない
そして何よりも重要なのは、「数字」ではなく「仕組み」で不動産投資を捉える視点です。
- キャッシュフローの健全性
- 管理品質
- 契約条項のリスク分析
これらを統合的に見直すことで、単なる“投資商品”ではなく、“事業”としての不動産経営が実現できます。
不動産投資は「始めること」よりも「続けていくこと」にこそ難しさがあります。リスクを理解した上で、計画的かつ柔軟に対応できる体制を整えていくことが、長期的な成功の鍵となるでしょう。





